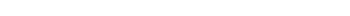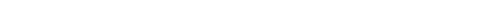このサイトは、脱炭素チャレンジカップ(旧低炭素杯)に参加された団体と、脱炭素チャレンジカップをサポートする企業と団体が連携した取組と活動団体のプロフィールが検索できます




- 検索結果
- 488件見つかりました
- 化石燃料に頼らない水素社会実現へ向けた実践的な環境教育

 沼津工業高等専門学校と静岡県立工業高等学校の共同研究委員会静岡県
沼津工業高等専門学校と静岡県立工業高等学校の共同研究委員会静岡県燃料電池に関する共同研究を推進し、小型燃料電池を動力源とするエコランカーの開発を行った。この成果を受けた県内の工業高校がそれぞれ活動することにより、日本初となる燃料電池自動車エコラン大会を開催し、水素社会実現へ向けた実践的なものづくり教育の成果を広く共有した。並行して、児童生徒へ向けた燃料電池体験教室を開催することで、地球環境保護に関する普及啓発活動を行っている。
高校エネルギー

- WEショップ(リサイクルショップ)を通じた資源循環活動

 NPO法人WE21ジャパン神奈川県
NPO法人WE21ジャパン神奈川県54の店舗で地域の市民から衣類や雑貨の寄付品をいただき、多くのボランティアの協力を得ながら販売し、売上の一部を国内外の支援金に充てている。リメイク講座も盛んで廃棄量の減量に寄与している。ショップで天ぷら油や携帯電話の回収も実施し、再資源化を図っている。拠点のある強みを生かし、フードドライブの取り組みも検討している。
NPO/NGOリサイクル・廃棄物利用
- 海の森を未来に届けるプロジェクト ~海の資源を無駄なく使う~

 一般社団法人海っ子の森主に 三重県 愛知県 山梨県
一般社団法人海っ子の森主に 三重県 愛知県 山梨県私達の食生活で大量のゴミとして処分されている海産生物の骨や貝殻、また、海中で異常増殖した侵略的外来種は、利活用されること無くゴミとなっています。本プロジェクトは、「海の資源( 生きものたちの死 )を無駄なく利用」を図るため、貝殻廃棄物や外来種を農業・畜産業に繋ぐ活動をしています。秋には「収穫祭」としてプロジェクト圃場で収穫された農産物や海の恩恵による交流会を開催しています。
団体職員リサイクル・廃棄物利用


- ゴミを拾う人はごみを捨てない。自然環境を守るのは貴方だ!!

 NPO法人秋田パドラーズ秋田県
NPO法人秋田パドラーズ秋田県カヌー体験による自然環境保全活動とクリーンアップを通した脱炭素3Rリサイクル社会の実現、各種イベント開催による地域活性化に取り組んでいます。 1、クリーンアップ103回、参加人数7,485人、回収ゴミは69.8t。 2、現状を知るための自然観察会139回、参加人数3,585人 3、学校講座や啓蒙活動が85回、参加人数3,609人 4、民間企業、行政からの要請イベントが498回、参加人数が16,042人
NPO/NGO森林保全


- 野心的な目標提起と丁寧な会員支援で、脱炭素化の取り組みを加速

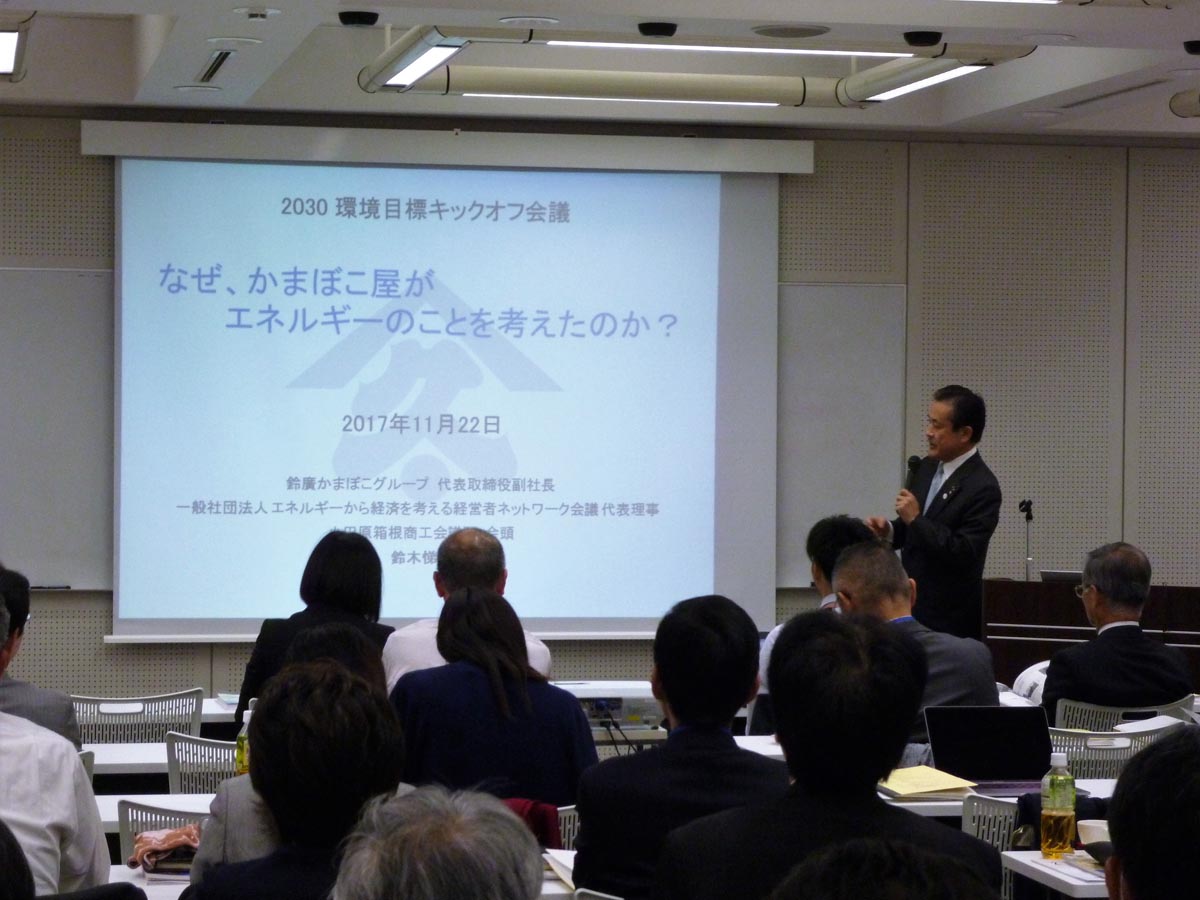 日本生活協同組合連合会全国
日本生活協同組合連合会全国脱炭素化の重要性は理解するものの、現場をもたない連合会(業界団体)が果たせる役割は少ないと思われがちです。そうしたなか日本生活協同組合連合会は、「持続可能な社会の実現」を理念に掲げる生協の連合会として、パリ協定など国際水準をふまえた温室効果ガス削減計画の策定を会員生協へ提起し、あわせてマニュアルの提供等を通じた細やかな支援を行うことで、生協全体での温室効果ガス削減の取り組みを推進してきました。
市民制度

- 「公園の利活用×地域協働」による低炭素社会実現への取り組み

 NPO法人エヌピーオー・フュージョン長池東京都
NPO法人エヌピーオー・フュージョン長池東京都0歳~100歳、子どもから高齢者まで、多世代・多様な人たちが、ユニバーサルに集まる場所が公園です。地域の一人一人が、地球温暖化防止活動などを通じた低炭素社会の実現に向けて、自分事として考え、実行に移すことが大切だと私たちは考えます。そのために、公園という開かれた場所を利活用し、地球温暖化活動防止などの取り組みにかかわる「仕組み」を構築し、『地域協働による低炭素社会の実現』を目指します。
NPO/NGO制度


- 地域の良いところを調べて、みがいて、活かす!

 太子町立中学校社会科学部大阪府
太子町立中学校社会科学部大阪府科学分野の活動では太子町の豊かな自然に目を向け、それに密着し、ホタルやカワバタモロコなどそこに生息している生物を対象に保全研究活動を行っている。また、社会分野では、地元の良いところを自ら取材し、記事を書き、それを紹介する手作りの情報誌「太子チャンネル」の発行を行っている。太子チャンネルは今では12号あり、毎号 800部ほど発行し温泉施設やコンビニ、役所等地域の様々な場所に配布し、親しまれている。
中学校森林保全


- エコマート~ぼくらの会社で未来を守ろう~

 橋本市立あやの台小学校エコマート和歌山県
橋本市立あやの台小学校エコマート和歌山県子どもたちが会社を設立し、企画した商品を販売し、得た収益を国際社会貢献のために寄付する活動を行います。昨年度は無農薬野菜を育てる会社、リサイクル手芸品を作る会社、壊れた木工品をリメイクする会社などが作られ、利益をフィリピンとインドのストリートチルドレン救済のために使いました。今年度は協力の輪を広げようと、アメリカ・ローナートパーク市や、関心を持ってくれた学校の子ども同士で交流を始めています。
小学校制度

- 『食べて守る琵琶湖の環境』地産地消・エシカル消費が地球を救う

 草津市立渋川小学校滋賀県
草津市立渋川小学校滋賀県本校児童は、6年間を通して身近な自然やくらし、文化とのつながりを学び、毎年、学習成果をまとめた「渋川ESDミュージアム」を校内に開館しています。特に5・6年生は、滋賀の食文化に学ぶことをテーマとし、地産地消の促進やエシカル消費が琵琶湖の環境保全だけでなく地球温暖化の防止にもなることを学びます。また、学校・地域・行政・企業等が協働して支援委員会を組織し、まちぐるみで児童の環境教育を支援してきました。
小学校地産利用・フードロス・食育

- 自然・人・物との関わりを生かした持続発展教育(ESD)の推進

 越谷市立大袋東小学校埼玉県
越谷市立大袋東小学校埼玉県「自然・人・物にやさしい東っ子の育成」を基本目標に掲げ、20数年以上にわたり環境教育に力を入れています。具体的な活動としては、(1)「総合的な学習の時間」「生活科」でのテーマ学習(2)環境の祭典「エコフェスティバル」、こどもエコクラブ活動(3)栽培活動、省エネ活動、ビオトープ保全活動の3つです。また、従来の環境教育に加え、ESDの理念を取り入れ、他教科でも関連した内容を系統づけて指導してます。
小学校市民協働
- バイオメタンを利用した新しい暮らしを提案する教育プログラム

 学校法人静岡理工科大学星陵中学校静岡県
学校法人静岡理工科大学星陵中学校静岡県本校ではバイオメタンに関する教育・研究活動を展開した。バイオメタンシステムでは、生ゴミなどの有機性廃棄物から可燃性ガスと液体肥料を生成することができる。これまでに、校内にバイオメタンを生成する施設の設置、出張講義や室内実験と発表会を実施することで、生徒への環境教育を展開した。また、生成したバイオメタンを聖火として燃焼するための活動、液体肥料で作物栽培を実施することで、生徒の課題研究活動を促進した。
中学校リサイクル・廃棄物利用

- SDGsの推進

 大田区立大森第六中学校東京都
大田区立大森第六中学校東京都本校はユネスコスクールのパイロット校として、国連持続可能な開発目標(SDGs)達成を推し進めるための活動を行い、特に気候変動について取組んでいる。全教科で課題解決するために環境を整え、各クラスにホワイトボード10枚、タイマー、環境NAVI、CO2排出量計測器、グリーンカーテンを設置し、ホタル復活プロジェクトとしてホタルの自生、洗足池環境調査、水質浄化活動、駅前花壇整備を意欲的に実施している。
中学校省エネ